「こども」という言葉、日常で何気なく使っていますが、
実は色々な表現があるって知っていましたか?
例えば、少しフォーマルな場面で「お子様」と言ったり、
親しい間柄では「坊や」「お嬢ちゃん」なんて言ったりもしますよね。
この記事では、そんな「こども」の様々な言い換え表現を、
それぞれのニュアンスやどんな時に使うのが適切なのかを、
具体例を交えながら、わかりやすく解説していきます。
「こども」という言葉を、もっと豊かに使いこなせるようになれば、
表現の幅が広がるだけでなく、
より相手に気持ちが伝わるコミュニケーションができるはず。
この記事を読めば、
「なるほど、こんな風に言い換えれば良いのか!」
と、すぐに実生活で使えるヒントが見つかるはずです。
さあ、一緒に「こども」の言葉の冒険に出かけましょう!
きっと、新しい発見があって、
言葉を扱うのが、もっと楽しくなりますよ!
「こども」の言い換え一覧

もしかしたら、あなたは「こども」という言葉を、いつも同じように使っているかもしれません。でも、ちょっと表現を変えるだけで、あなたの言葉はもっと豊かになるはずです。この記事では、日常会話や文章で「こども」を言い換えるための言葉をたくさん集めてみました。さあ、一緒に言葉の新しい扉を開けてみましょう。
| 言い換えの言葉 | 例文 |
| :———– | :———————————————————————- |
| 児童 | この図書館には、たくさんの**児童**向けの絵本があります。 |
| 幼児 | **幼児**は、まだ自分で靴を履くのが難しい。 |
| 子供 | 公園では、たくさんの**子供**たちが元気に遊んでいます。 |
| 子ども | **子ども**の成長は、本当に早いものですね。 |
| 少年 | **少年**は、将来サッカー選手になるのが夢だと言っていました。 |
| 少女 | 彼女は、**少女**のような可愛らしい笑顔が魅力的です。 |
| 若年者 | このプロジェクトは、**若年者**の雇用を促進することを目的としています。 |
| 未成年 | **未成年**には、お酒やタバコは販売できません。 |
| ガール | 彼女はいつも、**ガール**スカウトの活動を頑張っています。 |
| ボーイ | その**ボーイ**は、大きな声で歌を歌っていました。 |
| お子さん | 今日は、**お子さん**と一緒にピクニックに来ました。 |
| 子息 | 彼には、優秀な**子息**が二人いるそうです。 |
| 令嬢 | 彼女は、お医者様の**令嬢**で、とても上品な方です。 |
| 赤ちゃん | **赤ちゃん**の寝顔は、見ているだけで癒されますね。 |
| 乳幼児 | **乳幼児**の健康管理には、特に気を付けています。 |
| 坊や | その**坊や**は、いつもニコニコしていて可愛いですね。 |
| 娘 | 私の**娘**は、ピアノを弾くのが大好きです。 |
| 息子 | うちの**息子**は、スポーツが得意です。 |
| 言い換えの言葉 | 例文 |
|---|---|
| 児童 | この図書館には、たくさんの児童向けの絵本があります。 |
| 幼児 | 幼児は、まだ自分で靴を履くのが難しい。 |
| 子供 | 公園では、たくさんの子供たちが元気に遊んでいます。 |
| 子ども | 子どもの成長は、本当に早いものですね。 |
| 少年 | 少年は、将来サッカー選手になるのが夢だと言っていました。 |
| 少女 | 彼女は、少女のような可愛らしい笑顔が魅力的です。 |
| 若年者 | このプロジェクトは、若年者の雇用を促進することを目的としています。 |
| 未成年 | 未成年には、お酒やタバコは販売できません。 |
| ガール | 彼女はいつも、ガールスカウトの活動を頑張っています。 |
| ボーイ | そのボーイは、大きな声で歌を歌っていました。 |
| お子さん | 今日は、お子さんと一緒にピクニックに来ました。 |
| 子息 | 彼には、優秀な子息が二人いるそうです。 |
| 令嬢 | 彼女は、お医者様の令嬢で、とても上品な方です。 |
| 赤ちゃん | 赤ちゃんの寝顔は、見ているだけで癒されますね。 |
| 乳幼児 | 乳幼児の健康管理には、特に気を付けています。 |
| 坊や | その坊やは、いつもニコニコしていて可愛いですね。 |
| 娘 | 私の娘は、ピアノを弾くのが大好きです。 |
| 息子 | うちの息子は、スポーツが得意です。 |
「こども」の意味とニュアンス
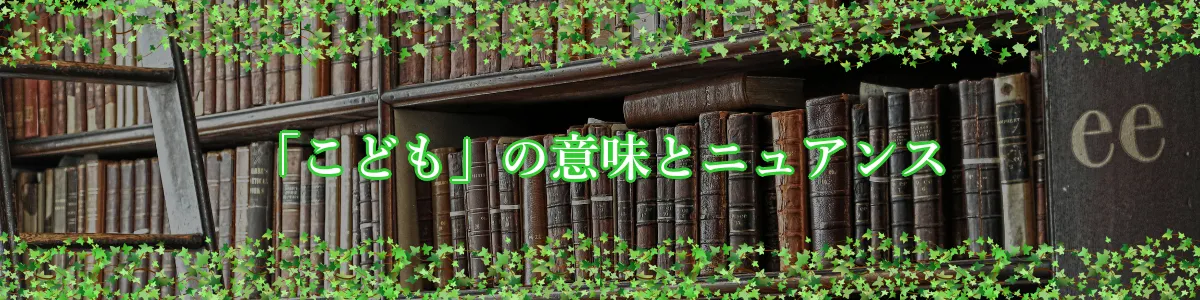
「こども」という言葉は、私たちにとって非常に身近で、日常的に使う言葉です。しかし、その意味やニュアンスを改めて考えると、意外と奥深いことに気づかされます。
まず、「こども」という言葉は、一般的に「成長段階にある未成熟な人間」を指します。具体的には、生まれたばかりの赤ちゃんから、小学校高学年くらいまでを指すことが多いでしょう。
しかし、「こども」という言葉は、単に年齢による区切りだけを表すものではありません。
そこには、無邪気さ、純粋さ、好奇心旺盛といった、大人にはない特別な性質が含まれていると捉えられます。
例えば、「子供のような笑顔」という表現は、大人の笑顔よりも、屈託がなく、純粋で、見る人の心を温かくするようなイメージがあります。
また、「子供の目線」という言葉は、物事を固定観念にとらわれずに、新しい発見をすることを意味します。
このように、「こども」という言葉は、年齢だけでなく、その人の持つ特性や状態を表す言葉として、私たちの感情や認識に深く影響を与えています。
また、「こども」という言葉を使う場面によって、ニュアンスが変わることもあります。
例えば、親が自分の子供を指すときに使う「うちの子」という言葉には、愛情や親しみが込められています。
一方で、社会的な文脈で「こども」という言葉を使う場合は、保護や教育の対象としての側面が強調されることもあります。
このように、「こども」という言葉は、状況や文脈によって様々な意味合いを持ち、私たちの日常会話や文章の中で、豊かな表現を可能にしてくれていると言えるでしょう。
「こども」の言いかえ表現
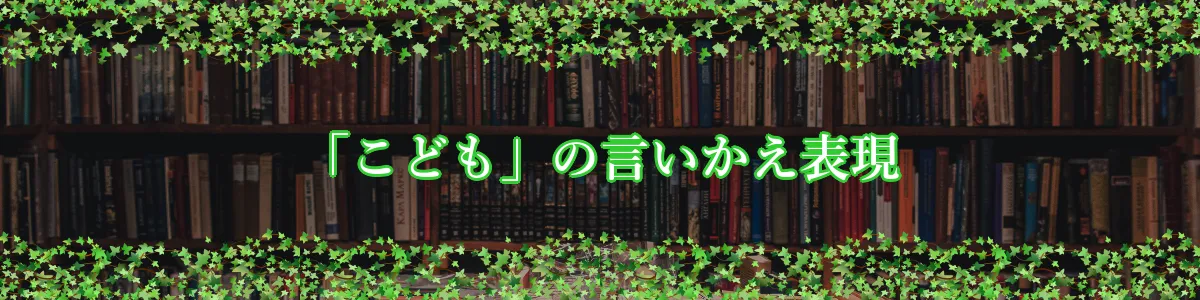
子どもの意味・使い方・例文
「子ども」は、一般的に生まれてから成長し、大人になるまでの人を指す言葉です。
年齢による明確な区切りはありませんが、未成年であることが多いです。
「子ども」は、親や養育者の保護を必要とする存在として認識されます。
【使い方】
「あの子はうちの子どもです。」
「子どもたちが公園で遊んでいる。」
【例文】
「子どもには無限の可能性がある。」
「子どもの成長は早い。」
子供の意味・使い方・例文
「子供」は、「子ども」とほぼ同じ意味で使われます。
漢字表記の「子供」は、少し硬い印象を与える場合や、公的な文書で使われることが多いです。
ひらがな表記の「子ども」よりも、少しフォーマルな場面に適しています。
【使い方】
「子供の教育について考える。」
「子供の頃、よく遊んだ場所。」
【例文】
「子供の権利を守る。」
「子供の未来のためにできること。」
児童の意味・使い方・例文
「児童」は、学校教育法で定められた小学校に在籍する子どもを指す言葉です。
一般的には、6歳から12歳くらいまでが「児童」とされます。
教育や福祉の分野でよく使われる言葉で、法律や行政用語としても用いられます。
【使い方】
「児童福祉施設」「児童手当」など。
「児童の健全な育成を図る。」
【例文】
「児童虐待をなくすために。」
「この施設は児童が安心して過ごせる場所です。」
幼児の意味・使い方・例文
「幼児」は、一般的に1歳から小学校入学前までの子どもを指す言葉です。
自分で歩いたり、簡単な言葉を話せるようになる時期の子どもを指します。
保育園や幼稚園に通う年齢の子どもも含まれます。
【使い方】
「幼児教育の重要性」「幼児向けの絵本」など。
「このおもちゃは幼児にも安全です。」
【例文】
「幼児の好奇心を育てる。」
「幼児期は心身の発達が著しい。」
生徒の意味・使い方・例文
「生徒」は、主に小・中学校、高等学校、専門学校などの教育機関で学ぶ人を指す言葉です。
先生から教育を受ける立場の人を指し、年齢は関係ありません。
学校に通っていることを前提とする言葉です。
【使い方】
「生徒会」「生徒指導」など。
「生徒たちは熱心に授業を受けている。」
【例文】
「生徒の個性を見つける。」
「生徒の意見を尊重する。」
学童の意味・使い方・例文
「学童」は、小学校に在籍する児童を指す言葉ですが、特に放課後に児童館や学童保育などで過ごす児童を指すことが多いです。
「学童保育」など、行政や福祉の分野でよく使われる言葉です。
【使い方】
「学童保育の利用」「学童クラブ」など。
「学童の安全を確保する。」
【例文】
「学童は放課後も楽しく過ごしている。」
「学童の健全な育成を支援する。」
キッズの意味・使い方・例文
「キッズ」は、英語の「kids」からきた言葉で、子どもたちを指すカジュアルな表現です。
年齢層は幅広く、幼児から小学生くらいまでの子どもに使われることが多いです。
親しみやすい印象を与えるため、商業的な場面やイベントなどでよく用いられます。
【使い方】
「キッズファッション」「キッズ向けイベント」など。
「この商品はキッズに大人気です。」
【例文】
「キッズの笑顔は宝物だ。」
「キッズたちが元気に遊んでいる。」
若年層の意味・使い方・例文
「若年層」は、比較的若い年齢層の人々を指す言葉で、年齢の範囲は文脈によって異なります。
一般的には、10代から30代くらいまでを指すことが多いです。
社会的な動向やマーケティングの分野で使われることが多く、若者の動向を分析する際に用いられます。
【使い方】
「若年層の消費動向」「若年層の雇用状況」など。
「若年層に人気のアプリ。」
【例文】
「若年層の投票率を上げる必要がある。」
「若年層の意見を積極的に取り入れる。」
青少年の意味・使い方・例文
「青少年」は、一般的に10代から20歳くらいまでの人を指す言葉です。
「青少年育成」「青少年健全育成条例」など、法律や行政、教育の分野でよく使われます。
心身ともに成長する大切な時期を指し、社会的な責任を負う前の世代です。
【使い方】
「青少年の非行問題」「青少年向けのプログラム」など。
「青少年は社会を担う大切な存在です。」
【例文】
「青少年の健全な育成を願う。」
「青少年のための支援活動。」
未成年者の意味・使い方・例文
「未成年者」は、法律で定められた成人年齢に達していない人を指す言葉です。
日本では、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、20歳未満の飲酒や喫煙は禁止されています。
法律や契約、権利の面で特別な扱いを受けることがあります。
【使い方】
「未成年者の飲酒は禁止されています。」
「未成年者の契約には保護者の同意が必要です。」
【例文】
「未成年者は法律で守られている。」
「未成年者の権利を尊重する。」
「こども」のシチュエーション別使い分け

年齢による使い分け
「こども」という言葉は、年齢によって使い分けが必要です。
一般的に、小学校入学前くらいまでの幼児を指すことが多いですが、小学生以上の子に対しても使うことがあります。
しかし、中学生以上になると「子ども」という表現が少し幼く感じられる場合もあるため、「学生」や「生徒」などの言葉を使う方が適切な場合もあります。
年齢が上がるにつれて、より大人に近い言葉を選ぶように意識しましょう。
成長段階による使い分け
「こども」という言葉は、成長段階によっても使い分けが必要です。
例えば、赤ちゃんや幼児期には「赤ちゃん」「幼児」といった言葉を使う方がより具体的に伝わります。
また、思春期を迎えた子どもに対しては、「子ども」という言葉が少し不適切に感じられる場合もあります。
その子の成長段階に合わせて、適切な言葉を選ぶようにしましょう。
場所による使い分け
「こども」という言葉は、場所によっても使い分けが必要です。
例えば、保育園や小学校などの教育現場では、「園児」「児童」という言葉がより適切です。
また、病院では「患者」という言葉が使われることもあります。
場所の状況やルールに合わせて、適切な言葉を選ぶようにしましょう。
関係性による使い分け
「こども」という言葉は、関係性によっても使い分けが必要です。
例えば、自分の子どもに対しては「うちの子」や「息子」「娘」など、より親しみを込めた言葉を使うことが多いでしょう。
また、他人の子どもに対しては、相手との関係性を考慮して「お子さん」や「〇〇ちゃん」など、丁寧な言葉を使うようにしましょう。
関係性に応じて、適切な言葉を選ぶことが大切です。
状態による使い分け
「こども」という言葉は、状態によっても使い分けが必要です。
例えば、病気や怪我をしている子どもに対しては、「病人」や「怪我をしている子」など、状態を具体的に表す言葉を使う方が適切です。
また、困っている子どもに対しては、「助けが必要な子」など、状況を把握しやすい言葉を使うようにしましょう。
子どもの状態に合わせて、適切な言葉を選ぶことが重要です。
場面による使い分け
「こども」という言葉は、場面によっても使い分けが必要です。
例えば、運動会や発表会など、特定のイベントや行事の場面では、「出場者」や「参加者」などの言葉を使う方が適切です。
また、何かを成し遂げた子どもに対しては、「頑張ったね」や「すごいね」など、労いの言葉を添えるようにしましょう。
場面に応じて、適切な言葉を選ぶことで、より気持ちが伝わりやすくなります。
フォーマルな場面での使い分け
フォーマルな場面では、「こども」という言葉は、少しカジュアルに聞こえる場合があります。
例えば、会議や講演会などでは、「未成年者」や「児童」「生徒」などの言葉を使う方が適切です。
また、文章では「子どもたち」という表現よりも「児童・生徒」や「青少年」などを使うように心がけましょう。
フォーマルな場面では、より丁寧で正確な言葉を選ぶことが大切です。
インフォーマルな場面での使い分け
インフォーマルな場面では、「こども」という言葉を親しみを込めて使うことができます。
例えば、友人との会話や家族との日常会話では、「うちの子」「〇〇ちゃん」など、より柔らかい表現を使っても問題ありません。
ただし、相手との関係性を考慮し、不快な思いをさせないように注意しましょう。
インフォーマルな場面では、相手との距離感に合わせて言葉を選ぶことが大切です。
文章での使い分け
文章で「こども」を使う場合は、読み手に誤解を与えないように注意が必要です。
例えば、学術的な文章やニュース記事などでは、「児童」「生徒」「青少年」などの言葉を使い、より正確に情報を伝えるように意識しましょう。
また、読みやすい文章を心がけ、必要に応じて具体的な言葉を補足するようにしましょう。
文章では、文脈に合わせて言葉を選ぶことが重要です。
会話での使い分け
会話で「こども」を使う場合は、相手の反応を見ながら言葉を選ぶようにしましょう。
例えば、相手が不快に感じていないか、言葉遣いが適切かどうかを常に意識することが大切です。
また、相手の年齢や立場を考慮し、失礼のないように言葉を選ぶようにしましょう。
会話では、相手に配慮した言葉遣いを心がけることが大切です。
特定の属性を強調する際の使い分け
「こども」という言葉を使う際、特定の属性を強調したい場合は、別の言葉を使うことを検討しましょう。
例えば、「障がいのある子ども」や「貧困家庭の子ども」など、特定の状況を伝えたい場合は、より具体的な言葉を選ぶ必要があります。
また、性別を強調したい場合は、「男の子」「女の子」などを使うことで、より具体的に伝えることができます。
特定の属性を強調したい場合は、言葉を選ぶ際に注意が必要です。
こどもの言い換えまとめ
こどもの言い換えまとめ
ここまで、様々な「こども」の言い換え表現を見てきました。
幼い子を指す「坊や」「お嬢ちゃん」といった愛らしい言葉から、少し成長した子を指す「少年」「少女」、さらに広い意味での「子どもたち」まで、そのバリエーションは実に豊かでしたね。
これらの言葉を使い分けることで、文章にニュアンスや感情を込めたり、読者に具体的なイメージを伝えたりすることができます。
今回の記事が、みなさんの表現の幅を広げるための一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
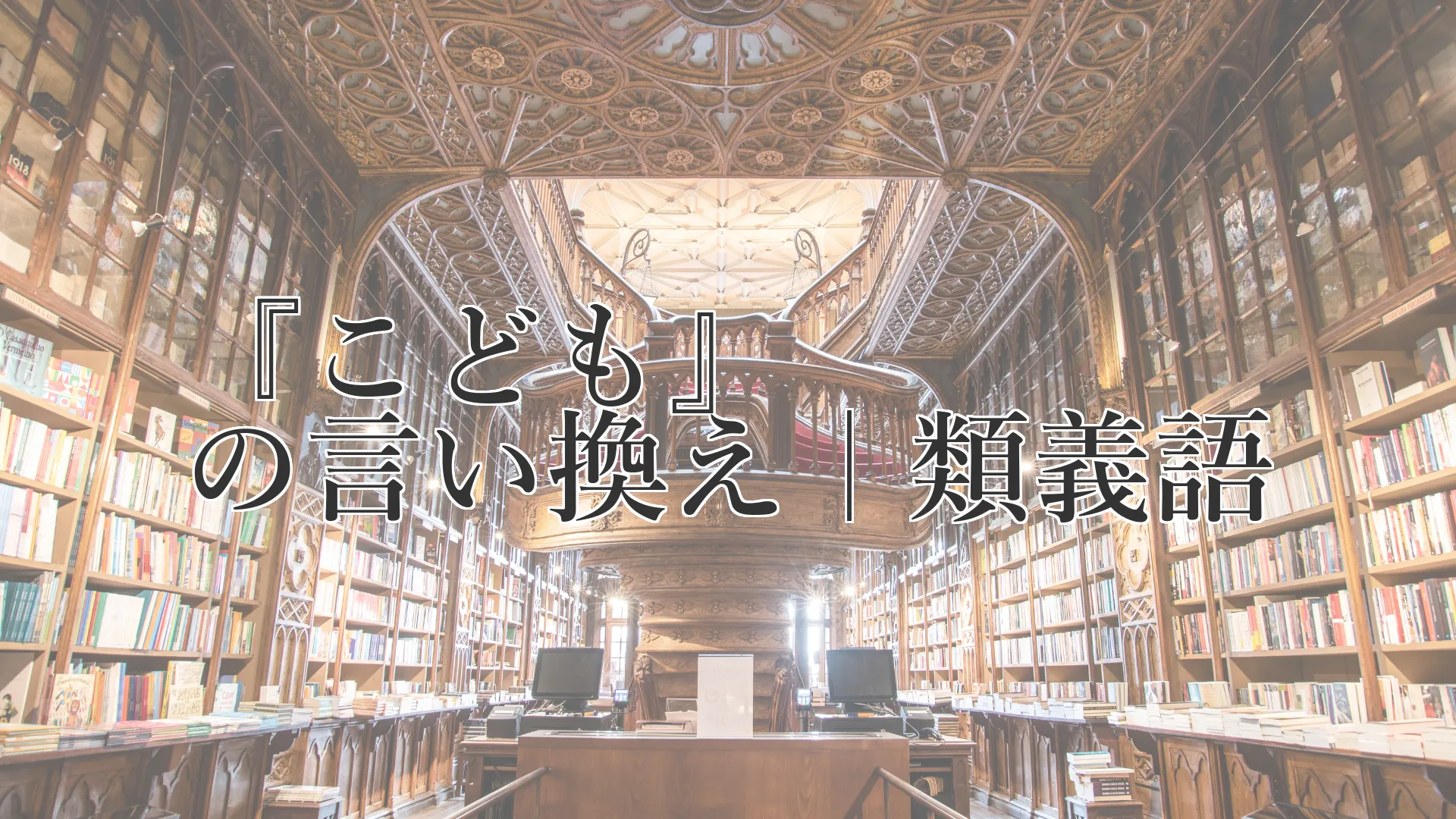
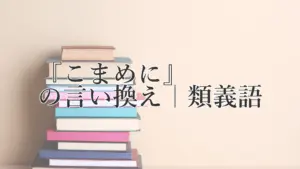
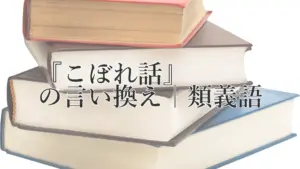
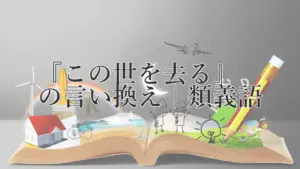
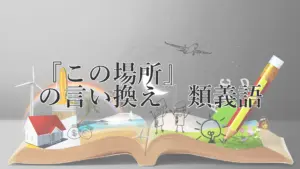

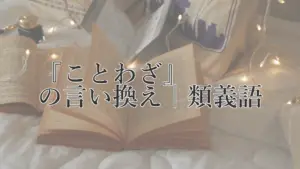
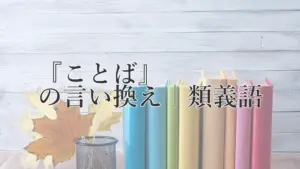
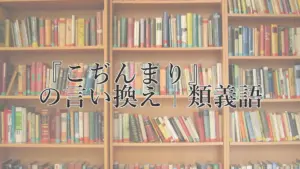
コメント